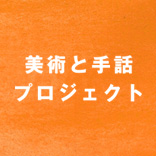3/2(日)に企画展「MOTアニュアル2024 こうふくのしま」に関連した、
東京都現代美術館のプログラムを、美術と手話プロジェクトが企画・運営を
行いました。
★開催日時:2025年3月2日(日) 14:00~15:30
★会場:東京都現代美術館 企画展示室2、3階
★企画展「MOTアニュアル2024 こうふくのしま」
URL:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-annual-2024/
この企画は聞こえない人、聞こえにくい人、聞こえる人、と多様な参加者が集まる中、
ファシリテータを美術と手話プロジェクトの西岡が受け持ちました。
参加者のみなさまが対話を楽しめるように、スライドやフリップなどのツールを用意し、
手話通訳や文字情報等のフォロー、美術館側で用意した聞き取りをサポートする機器を
活用しつつ、展覧会担当の学芸員・楠本愛さんも交えておしゃべり鑑賞会をしました。
鑑賞企画についての説明を行い、参加者たちに自己紹介をしていただいた後、
企画展示室3階にて、参加者たちにフリップを使ってメッセージを出しつつ、
庄司朝美さん、清水裕貴さんの作品を鑑賞。
そして、作品鑑賞の感想や印象に残ったことなど、みんなで自由にトーク。
庄司朝美さんの展示室では、こわい、不気味、と感じる人も多いようです。
しかし、個人的には、彼女の作品は観れば観るほど、さまざまな気づきが得られ、
とても面白いものだと感じていたので、みんなにそういう部分に気づくように、
作品をじっくりと鑑賞していただきたくて、

と、メッセージを出してみました。
庄司さんの展示室のあるコーナーをみんなで囲んでのおしゃべりでは、
最初、こわいと感じるコメントが多かったのですが、
・身体が透けてみえるような描き方から、いろいろと感じることがある
・展示室を進行方向にみていくと色彩の変化から暖かく感じてくるようになった
・展示室にある双眼鏡を通して作品をみると新しい発見ができて面白い
というさまざまな方向から話が出てきて、話がどんどん膨らんでいきました。

写真提供:東京都現代美術館
清水裕貴さんの展示室は、暗くいろいろな音が入り混じる中での鑑賞になるため、
観ながらのおしゃべりはとても難しい。(暗いと聞こえない人は手話や口形など、
よみとりができなくなってしまう)
それで、清水さんの展示室では各自で自由に観ていただき、企画展示室2階にて
作品をモニターでみせながらおしゃべりする形をとりました。
清水さんの作品は、中国の大連、東京の海岸を舞台にしたインスタレーション。
「国内で撮影された作品は、中国の海で海水などでネガを劣化させている」
という楠本さんの話から、わざわざこんなことをするのはどういった意図が
あるのか、など、参加者が感じたことを語り合いました。
そんな中、参加者の一人から、
「この会で鑑賞する中で、この展覧会のタイトルが『こうふくのしま』となって
いるのはどうしてなの?「こうふく」が連想できる感じがなく、気になっている」
という発言がありました。
それについて楠本さんから、展覧会のタイトルについて、
・最後の部屋に展示されている100年前の作品、《幸福の島》から引用
・《幸福の島》は、作品から社会的に複雑な背景を感じ取ることができる
・この展覧会は複雑な現実をどう見るかということをテーマにしている
と説明をいただきました。

国吉康雄《幸福の島》1924年頃
展覧会のタイトルに入っている「しま」について、
参加者たちは、作品を通して、このおしゃべり鑑賞会での対話を通して、
それぞれが思いをめぐらせたのではないでしょうか。
この企画は、聞こえない人、聞こえにくい人、聞こえる人、と多様な参加者が
それぞれ手話、文字情報、音声など、各自が自分にあった方法で話を聞き、
「自分の言葉」で発言していました。
会の後、聞こえにくい参加者たちから、
「楽しかった。ありがとう。またこのような企画を期待しています!」
と言葉をいただきました。
情報保障とクリエイティブ。
鑑賞企画を行うにあたって、双方の適切なバランスをとるのはとても難しい。
個人的には、文化の違う人間たちのいる海の向こうにある「しま」を
みているような、そんな気持ちになることもたびたびあります。
そういう中で今回の企画で《幸福の島》の作品を通して国吉さんが、
悩むわたしに問いかけてきているような、そんな気持ちになりました。
今後もさまざまな美術館、そして企画に参加してくださるみなさまと協力しつつ、
多様な人がともに楽しめるような企画を行っていきたいと考えています。
文:西岡克浩